肺炎と言えば、多くの高齢者が命を落とす原因として認識されています。特に、新型コロナ(COVID-19)は重症の肺炎を引き起こすということで、世界中で恐れられてきました。ただ、肺炎を引き起こす原因となる感染症には、新型コロナ以外にもいろいろなものがあります。
ここでは、本ブログ「https://www.uirusu24.org」で、2024年7月21日に載せた記事(「バムサジャーナルに掲載された総説―肺炎と感染症―」の転載記事)について、少し分かりやすく解説しました。
肺炎の原因となる病原体による分類
- 細菌性肺炎を引き起こす病原微生物
- 肺炎球菌:肺炎を引き起こす代表的な存在として名前にも「肺炎」がついています。特に、 小児と高齢者にとっては命取りにもなりかねません。肺炎球菌は少なくとも100以上もの血清型があります。血清型が異なるということは、ある型の肺炎球菌の感染によって誘導された抗体は、その型の肺炎球菌に対する感染防御能を持っていますが、同じ肺炎球菌でも別の型に対しては感染防御能を持っていません。同様に、いろいろな肺炎球菌ワクチンが開発されていますが、それぞれのワクチンに含まれる肺炎球菌の型に対する感染防御能ワクチン接種で誘導された抗体の感染防御能は、それぞれのワクチンに含まれていた型のみに対応できます。しかし、同じ肺炎球菌であっても、別の血清型(ワクチンに含まれていない型)の肺炎球菌に対しては感染防御として機能しません。そもそも肺炎球菌は、鼻や喉の奥に棲んでいます。このような肺炎球菌は常在菌と呼ばれるもので、病原性とは無関係な細菌です。このように、細菌を常在させている人は保菌者と呼ばれ、日本人の高齢者の約3~5%、一方乳幼児では20~50%と高率に保有していると言われています。したがって、咳をすることで飛沫感染により周囲の人にうつす可能性があります。
- インフルエンザ桿菌b型(Hib):主に気道に感染し、肺炎や敗血症を引き起こすことがあります。肺炎球菌と同様、無症状の状態で鼻の粘膜に保菌している人がいます。したがって、飛沫感染で人から人へうつっていきます。小児では、細菌性の髄膜炎など、重症化する典型的な細菌です。Hibワクチンは、2013年4月から定期接種になっています。
- 緑膿菌:自然環境で広く存在しています。この細菌も、ヒトの皮膚や気道にも常在していますので、院内肺炎や誤嚥性肺炎の原因となっています。
- 黄色ブドウ球菌:黄色ブドウ球菌は、皮膚や消化管内などの体表面に常在しています。通常は無害ですが、感染した人の免疫状態が低下した状態では肺炎を引き起こすことがあります。
- 非定型肺炎を引き起こす病原微生物
- マイコプラズマ:マイコプラズマ感染症はマイコプラズマ・ニューモニエという菌が原因となっています。この菌に対しては、抗生剤が有効で、他の細菌と同様ですが、通常の最近とは異なって、自らの力だけでは増殖できずに宿主細胞に入り込んで増殖するという、ウイルスに近い生活環を採ります。6~12歳の小児に多く見られる感染症で、潜伏期は2~3週間と長いです。頑固な咳が続く症状が特徴です。
- クラミジア:クラミジア感染症によって引き起こされる肺炎の原因菌には、肺炎クラミジアとトラコーマ・クラミジア、そして人獣共通感染症である、オウム病の原因となるクラミジア(オウム病クラミジア)があります。肺炎クラミジアは飛沫感染によって市中肺炎(後述)の原因となるのに対して、トラコーマ・クラミジアによる肺炎は、これに感染している母親から生まれる時に産道感染するので、新生児や乳児の発症が多くみられます。オウム病クラミジアは、オウム以外にもインコやドバトも感染していることがあり、これらの鳥の乾燥した分泌物や排泄物を吸い込むことで肺炎を引き起こす可能性があるので、注意が必要です。
- レジオネラ属菌:水や土壌に生息しているレジオネラ属菌に感染すると、軽症から重症の肺炎(レジオネラ肺炎)を引き起こすことがあります。特に、高齢者が温泉に行った後1週間ほど(潜伏期間は2~10日)で倦怠感や頭痛などの症状が現れることがあると、レジオネラ肺炎が疑われます。
- ウイルス性肺炎を引き起こす病原微生物
- インフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルス、ヒトメタニューモウイルス:インフルエンザウイルスに感染しても、喉や鼻の粘膜で増殖する程度で、軽い症状で終わる場合が多いです。しかし、免疫応答能が弱い乳幼児や高齢者では、インフルエンザウイルスに感染すると喉や鼻にとどまらず、肺にまで達する場合があります。このような場合では、時には肺炎を引き起こすことがあります。
- インフルエンザ後の肺炎球菌感染症:インフルエンザウイルスが侵入してきた際は、まず空気の通り道である気道の表面の粘膜細胞に付着し、その粘膜細胞で猛烈な勢いでウイルスを大量に産生します。その結果、感染した気道の細胞は壊されてしまい、粘膜の粘液と繊毛の機能(喉の方に押し出す、肺胞マクロファージによる処理)が働かなくなります。この状態になると、呼吸で吸い込んだ空気中に含まれる病原体や、喉に棲みついている肺炎球菌などが肺に到達するのを防ぐことができなくなります。インフルエンザウイルス感染後に、最も多く見られる肺炎の原因となる病原体は肺炎球菌です。特に、65歳以上の高齢者では、インフルエンザウイルス感染後の肺炎球菌感染により、重症の肺炎になって命を落とす頻度が高いことが知られています。
- 新型コロナウイルス:健康で免疫応答能もしっかり機能している人であっても、初めて遭遇するウイルスである新型コロナウイルスに対する免疫(特異的な免疫)は持っていません。そのためウイルスに感染後、このウイルスを大量に増殖させてしまい、重症化に陥ることが相次ぎました。特に、感染した人が基礎疾患を持っている場合には肺炎を引き起こしやすく、さらに肺から血液へウイルスが侵入すると全身症状が引き起こされ、死亡する場合が多くみられました。しかし、感染・増殖を繰り返す期間が長くなるにしたがって、ウイルスの遺伝子に変異が引き起こされやすくなり、その結果としてウイルスの弱毒化が進みました。このようにして、重症化へと進む肺炎になる率が徐々に下がってきており、今ではほぼインフルエンザウイルスに近い位置づけになりつつあります。
- サイトメガロウイルス:前述のウイルスは、体外からの侵入によって感染(外因性感染)するのが一般的です。これに対して、ヘルペスウイルスの一種であるサイトメガロウイルスは、新生児期に野外に存在しているウイルスに自然に感染し、そのほとんどの場合は無症状のまま経過します。その後もほぼ症状がない状態で、体内に潜伏感染し続けています。この潜伏状態を維持できるのは、体の免疫応答能が正常に機能して、ウイルスが活性化するのを抑え込んでいるからです。しかし、臓器移植を受ける人やAIDS患者などは免疫抑制状態になっています。免疫抑制下、すなわち潜伏していたウイルスの活動を抑える免疫応答能が低下することにより、潜伏していたサイトメガロウイルスの活動を許すことになります(内因性感染)。活動を開始したサイトメガロウイルスは、肺炎を引き起こし、重症化しやすい結果となります。
- 麻しんウイルス:麻しんウイルスの感染は2回の麻しんワクチンの接種で防げます。しかし、ワクチン未接種の場合では容易に感染します。免疫応答能力が低い乳幼児、また低下している高齢者や妊婦が麻しんウイルスに感染しますと、合併症として肺炎が引き起こされ、重症化します。
- 肺真菌症を引き起こす病原微生物
- 肺真菌:真菌(カビの仲間の総称)は水虫やタムシなど、皮膚病の原因になることが一般的な認識ですが、このカビが肺炎を引き起こす病原体になる場合があります。カビは環境の至る所に存在し、空気中にも浮遊しています。ステロイド剤や免疫抑制剤を投与されている人やがん患者、AIDS患者、糖尿病患者、喘息患者など、免疫抑制状態にある人の場合、呼吸して空気中のカビを取り込むことで、稀に肺炎を引き超す場合があります。特に、問題なのは肺アスペルギルス症で、重症化しやすいと言われています。
感染する場所で分類される肺炎
- 市中肺炎:日常生活を送っている人々の間で起こる肺炎です。健康に日常生活を送っている中で、社会環境中のどこかで肺炎を引き起こす病原体に感染していることを意味しており、市中肺炎の原因になることは、その病原体が社会で広がっていることのサインになります。主な病原体は、肺炎球菌(全体の20%近い)、Hib、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、クラミジア、マイコプラズマ、レジオネラ属菌、新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルスなどです。
- 院内肺炎:入院後48時間以上経過してから起こった肺炎です。そもそも何らかの疾患で入院している患者に起こる肺炎なので、市中肺炎の対象の健康体とは異なり、基本的に重症化しやすいです。主な症状は、咳・痰・発熱・倦怠感・息苦しさなどです。院内での感染が原因となりますので、市中肺炎の原因菌とは異なり、黄色ブドウ球菌、大腸菌、Hib、クレブシエラ桿菌、プロテウス菌、エンテロバクター菌、緑膿菌などが原因菌となります。
その他の肺炎の分類
ヒトの肺は、成人では3億から6億個もの、肺胞(直径約0.3 mm)と呼ばれる小さな袋状の構造で構成されています。呼吸することで新鮮な空気はこの肺胞内に送られます。ただ、加齢とともにその数は減少していきます。肺胞の周りは間質で埋められ、ここに肺毛細血管が張り巡らされており、酸素と二酸化炭素の交換が行われています。細菌性肺炎は肺胞内で炎症が起こることが多く、もう一方のウイルス性肺炎は間質で炎症が起こることが多くあります。
- 肺胞性肺炎:肺胞性肺炎とは、肺の小さな袋状の構造である肺胞に炎症が起こる病気です。肺胞は酸素と二酸化炭素を交換する場所ですので、肺胞性肺炎になるとこの交換がうまくできなくなり、呼吸困難などの症状が現れます。肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、Hibなどの細菌が感染した時に多く見られます。他にも、ライノウイルス、アデノウイルス、RSウイルスなどのウイルス、さらにマイコプラズマによっても引き起こされます。
- 間質性肺炎:肺胞を取り囲む間質に炎症や繊維化が起こると、瘢痕化と硬化につながる場合もあり、最終的には回復することが困難で、肺の機能低下を招くことが多い状態になります。サイトメガロウイルス、EBウイルス、単純ヘルペスウイルスなどのウイルス感染時に多く見られます。他にも、結核菌、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエなどの細菌、そしてアスペルギルスなどの真菌などでも引き起こされます。
- 誤嚥性肺炎:2020年の初めに新型コロナが出現して以来、マスクをつけることと丁寧な手洗いを励行し、熱がある場合や咳が出ている状態では戸外に出歩かないようにする、というのが一般的でした。このような状態が2~3年も続きました。これを続けた結果、高齢者の多くは喉の筋肉(ノド筋)の機能低下が進んでいると言われています。食事で口から入った食べ物は胃の方(食道)へ、呼吸で鼻や口から吸いこんだ空気は肺の方(気管支)へ行くように調節しているのが喉の筋肉です。呼吸器の病原体が多少胃に入っても、胃酸で病原体をやっつけることができます。しかし問題は、喉の筋肉の衰えで正確な調節ができずに、食べ物が肺に入った場合には炎症が発生することです。このように、間違えて嚥下することが原因となるので、誤嚥性肺炎と呼ばれています。ただ、食事中の誤嚥だけではなく、寝ている間に唾液が喉に棲みついている肺炎球菌などと一緒に肺に侵入する(肺に落ちる)など、本人はもちろん、家族など周囲の人も気づかない状態で、いつの間にか誤嚥していることがありますので、油断なりません。 最近、盛んに注意喚起されるのが、高齢者は口の中を清潔にする口腔ケアです。
- 小児・新生児肺炎:子どもの呼吸がつらそうだったり、顔色が悪くなったり、またぐったりしているなど、普段と様子が異なり、発熱や咳などの異常が認められれば肺炎が疑われます。インフルエンザウイルスや肺炎球菌が原因となることが多いです。他に、RSウイルスの感染は3歳ぐらいまでが多く、5歳以上ではマイコプラズマが多いとされています。新生児肺炎は、生後28日未満の新生児に起こる肺炎のことです。上記のような細菌やウイルスなどに感染することが原因となりますが、まだ免疫機能が確立していない状態であることで、非常に重症化することが一般的です。
- 侵襲性肺炎:肺炎球菌感染症で最も注意が必要なのは、侵襲性肺炎球菌感染症(本来は無菌状態である血液や髄液から、肺炎の原因となる肺炎球菌が分離される症状)で、血液から分離された時は敗血症(感染症が原因で全身に炎症反応が起こる状態)、髄液からの場合は髄膜炎と呼ばれます。2歳未満の小児と65歳以上の高齢者に多く、この状態になると重症化を招くことが一般的です。小児の場合、肺炎を伴わずに発熱の初期症状から敗血症、髄膜炎、さらに肺炎球菌性の中耳炎後に侵襲性の肺炎に至る場合があります。高齢者の場合、菌血症(血液の中に細菌がいる状態のことで、敗血症への引き金になる場合があります)では発熱、咳、喀痰、息切れなどの症状、髄膜炎では頭痛、発熱、けいれん、意識障害、髄膜刺激症状などの症状を示します。
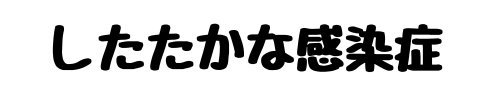
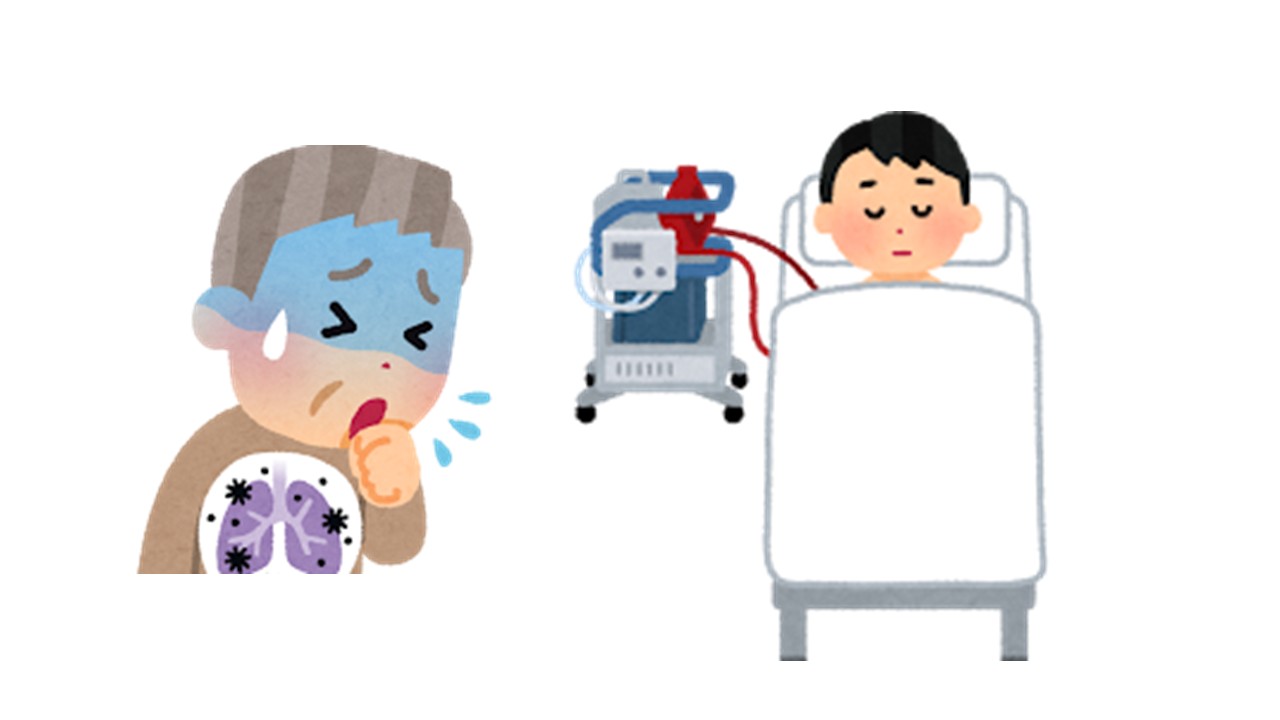


コメント